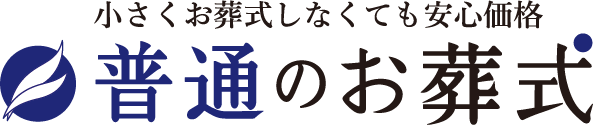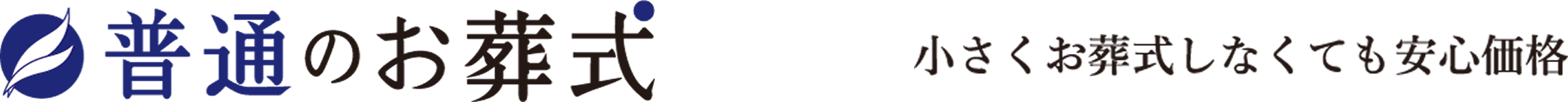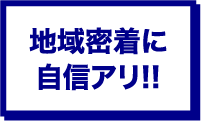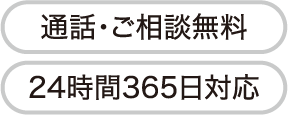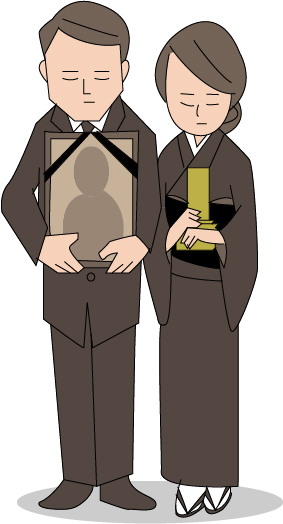
喪主(もしゅ)と施主(せしゅ)の違いは?
葬儀において、「喪主」という役割は重要な位置を占めていますが、もうひとつ「施主」という役割があることをご存じですか?両者には明確な違いがあります。ここでは、それぞれの役割や責任について詳しく解説します。
喪主の役割
喪主は、葬儀の中心となる人物で、故人の家族や親族の代表として葬儀全体を取り仕切る役割を担います。一般的には「喪主」=「施主」という全てを一人で行う形が当てはまりますが、状況によっては「喪主=葬儀を取り仕切る」「施主=葬儀費用など金銭的な管理」と役割が分けられることがあります。
喪主の役割として以下のようなことがあります。
- ①葬儀全体の管理
- 明確な定義はありませんが喪主は通常、故人と最も血縁関係の近しい関係にある人物が務めることが多いです。例えば、配偶者、長男または長女、あるいは親などが選ばれることが一般的です。また必ずしも喪主は一人という決まりはなく2名で喪主を執り行うこともあります。主な役割としては、葬儀社との打ち合わせ、親族への連絡や対応、参列者への挨拶や葬儀を執り行う宗教者への対応があります。
- ②葬儀の挨拶
- 通夜・お葬式の中での親族や参列者への挨拶の機会がありますが、もっとも大事なのはお葬式の最後に家族の代表として参列者に対して感謝の意を述べたり、故人との思い出を共有したりする挨拶を行います。その場で挨拶を考える方もいますが、スムーズに行えるよう事前に準備をして読み上げる形でも問題はありません。
- ③葬儀後の対応
- 葬儀後の後返しとしての返礼品の準備、や感謝状の送付なども喪主の責任として行われることが多いです。
施主の役割
一方で、施主は、葬儀の費用を負担し、実際の運営における決定を行う役割を担います。
施主の役割は以下の通りです:
- ①費用の負担
- 施主は葬儀の予算を管理し、葬儀社への支払いの管理や僧侶へ渡すお布施の準備を行います。
- ②香典や供物の管理
- 香典を誰からいくら頂いたのか、誰から供物や弔電を頂いたかのリスト作成や弔問客の記帳のまとめを行います。
- ③喪主の補助
- 喪主が不在時に替わりの代表として弔問客の対応をしたり、法要の準備を行うなど、負担の大きい喪主の補助も施主の大きな役割となります。
喪主と施主が異なる場合の一例
- ・連れ添いが高齢者の場合
- 世帯主が亡くなった場合、故人の妻が高齢で実務的な責任を果たすのが難しい為、子供が喪主を務め、施主として故人の妻が付くことがあります。その他にも兄弟で喪主と施主を分ける等、家族の関係性により様々な形が想定されます。
- ・特定の宗教や地域の習慣
- 地域や宗教の習慣によって、役割が分担される場合があります。
喪主と施主の協力体制が大事
喪主と施主は、葬儀において重要な役割を果たす存在ですが、その責任や立場には違いがあります。喪主は主に精神的な代表として、施主は実務的・経済的な責任者としての役割を果たします。葬儀を円滑に進めるためには、両者が協力し合うことが大切です。葬儀を計画する際には、家族や親族と十分に話し合い、適切な人を喪主や施主として選ぶことが重要です。
「普通のお葬式」では様々なご相談、ご紹介を承っております。
普通のお葬式では、お葬式、法事、終活に関するお困りごとなど、様々な専門知識を要する内容のお手伝いやご紹介させて頂いております。「普通のお葬式お客様サポートダイヤル(0120-333-841)」まで、お気軽にお問い合わせください。詳しくはこちらから。
普通のお葬式 | わかりやすい料金で「ふつう」にお葬式
関連コラム
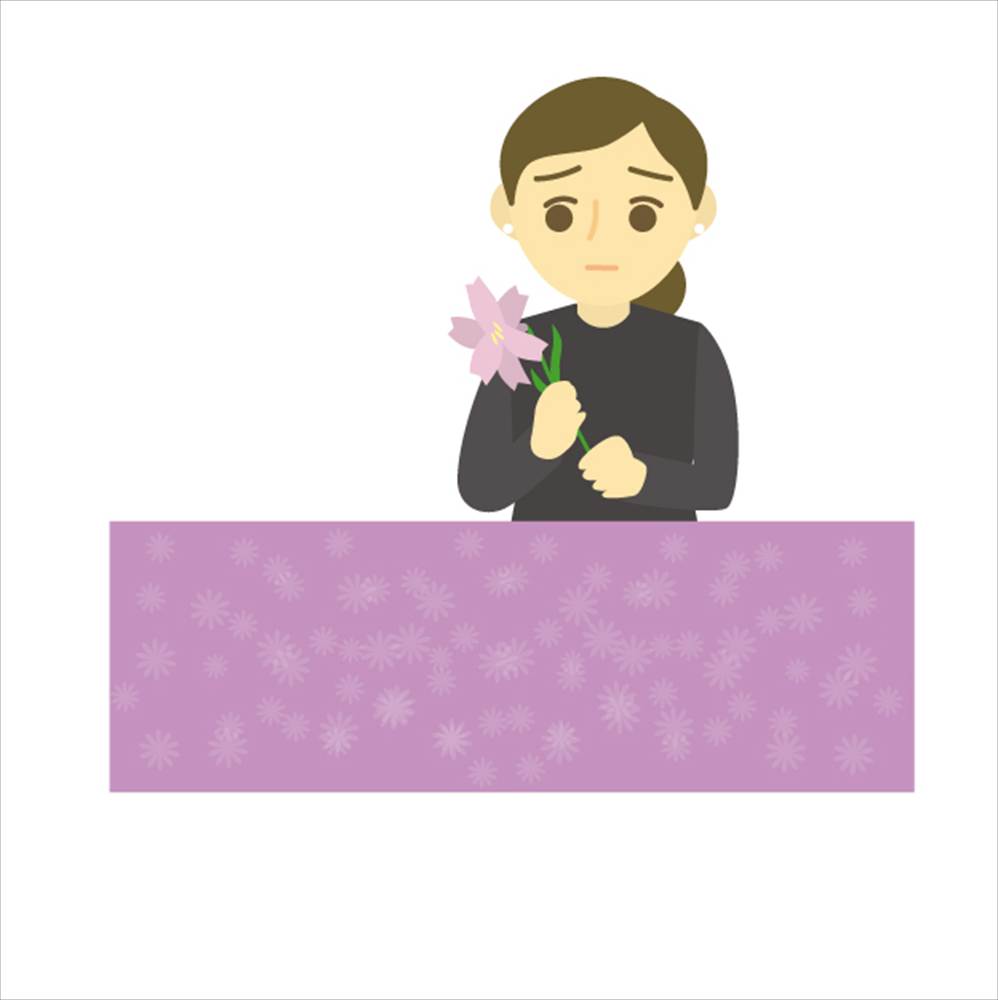
棺の中に入れていい副葬品について
お棺のふたを閉じる前に故人との「思い出の品を一緒にいれてあげたい」というご遺族は多いと思いますが、棺の中には何を入れていいのか・・・ダメなのか・・・

家族葬と一般葬の違いとは?
最近では「家族葬」でお葬式を依頼される方が増えています。一般葬(普通のお葬式)と家族葬は何が違うのでしょうか

お葬儀やお通夜にて流すBGMについて
葬儀会場では、よく館内で曲を流したり演奏をしたりします。葬儀やお通夜でのBGMを流す理由は?タイミングなど?曲選びの注意など?普段何気ないBGMについてのお話です。

お葬式にまつわる迷信
お葬式は故人を送り出す厳粛な儀式であると同時に、古くから数多くの迷信が語り継がれています。これらの迷信には、死を恐れ、魂の世界に敬意を払う人々の心理が反映されています。現代では迷信を信じる人が減ってきましたが、地域や家庭によっては今でも重要視されています。本記事では、代表的なお葬式の迷信をいくつかご紹介します。