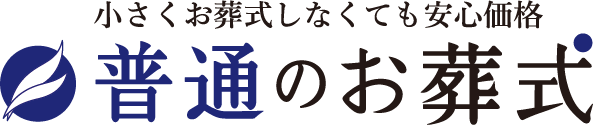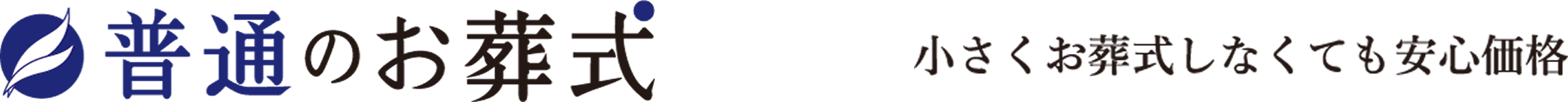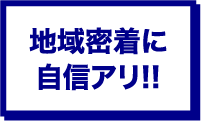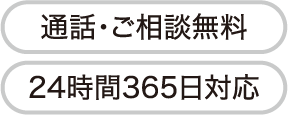お葬式でのお悔やみの言葉
お通夜・ご葬儀で喪主・ご遺族にどうやって声をかけたらよいのか。。。ご遺族を想うと気軽には声を掛けづらいし、普段とは違う場所だけに、言葉遣いに戸惑う方も多いと思います。ここではお悔やみの言葉の伝え方、お悔やみを伝える際に気をつけること、状況に合ったお悔やみの言葉、ご遺族にかける言葉をご紹介します。
お悔やみの言葉は短く簡潔に
お悔やみの言葉は短く簡潔にまとめることが大切で、言葉の例として、次のようなものが挙げられます。
「この度はお悔やみ申し上げます」・「この度はご愁傷様です」・「哀悼の意を表します」
「この度は大変なことで」・「ご冥福をお祈りします」
※「ご冥福」はキリスト教・浄土真宗などのご葬儀では、宗派の教義にそぐわないため、使わないようにします。
ご遺族は多くの弔問客に対応せねばなりません。あまり長々としたものでは相手を疲れさせてしまいますので、配慮をもって簡潔にお伝えすることが重要です。
使ってはいけない“忌み言葉”
お悔やみを伝える際に気をつけること、それは「忌み言葉を使わない」ことです。「重なる」「続く」「再び」など、不幸が続くことを連想させる言葉、「たびたび」「またまた」というような言葉を繰り返す「重ね言葉」は忌み言葉と言われているため、使用を避けます。また、病状や死因を聞くことは、ご遺族にとっては辛い時のことを思い出させてしまうことになりかねないので控えます。※ご高齢の方が亡くなった場合、「大往生」という言い方をすることもあります。ただ、参列者側が使うのはNGですので、ご遺族に対してのお悔みの言葉としてはふさわしくありません。
気遣いのある一言を
あまり気にしすぎると、ありがちな言葉しか使えず、他人行儀な印象を与えかねません。ご紹介したお悔みの言葉は基本的なものであり、その時々の状況によって変わります。「自分が同じ立場だったら言われたくない」と思うような言葉は避け、自分の言葉に気持ちを乗せて伝えることが、ご遺族の心にとどく言葉になるポイントです。
関連コラム
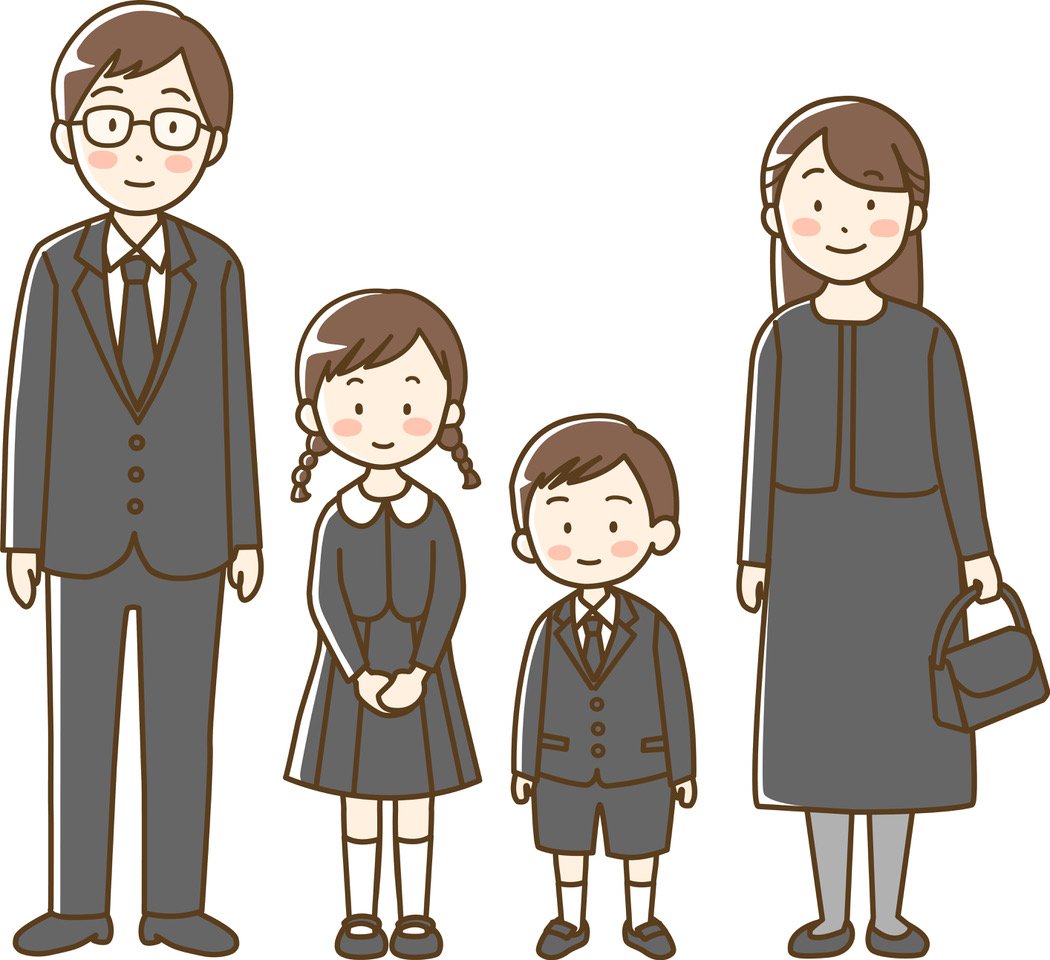
お子様を連れてお葬式に参列するときは
小さなお子様を連れての参列する場合のマナーなど問い合わせをいただくことがありますのでポイントをご紹介します。よくあるご質問は「服装はどうしたらよいでしょう?」「連れて行く親としてのマナーや心掛けは?」「小さい赤ちゃんでも連れていっても良いのか?」などが多いです。

弔意の伝え方
普通のお葬式では家族葬プランもご用意しておりますが、最近では家族葬という事で香典を辞退する形式も増えています。香典辞退を伝えられた場合、香典以外で弔意を示す方法をご案内します。

お葬式での言葉遣い
お葬式へ参列する時、ご遺族への対応や遺族側から参列していただいた方へのマナーや配慮はとても重要です。つい出てしまう言葉、控えた方が良い言葉などをご紹介します。

お悔やみの言葉に迷ったとき――失礼にならない考え方
お悔やみの言葉は、正解が分からず迷ってしまう方も少なくありません。失礼にならないために大切な考え方や、言葉を選ぶ際のポイントを分かりやすく解説します。