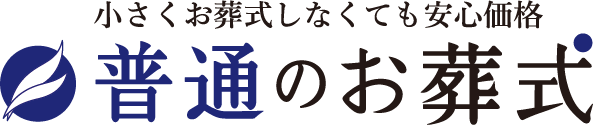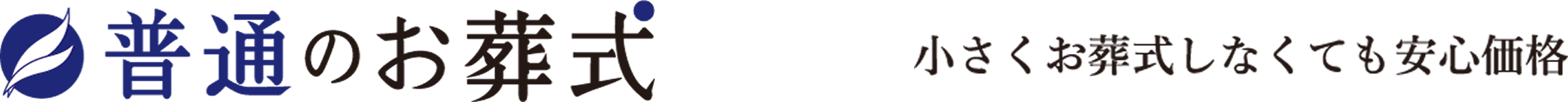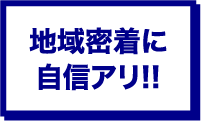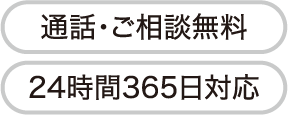大切にしてきた人形の処分に困る時
子どもの成長を見守ってきた雛人形や五月人形、思い出の詰まったぬいぐるみ。「捨てるのは忍びないけれど、どうしたらいいのだろう」と迷う方は少なくありません。そんな時に選ばれるのが「人形供養」です。
人形供養とは何か
人形供養とは、役目を終えた人形やぬいぐるみをお焚き上げや読経で供養し、感謝を込めて見送る儀式です。
古来より、日本では物にも「魂が宿る」と考えられてきました。
長年大切にした人形をただゴミとして処分するのではなく、きちんと供養して手放すことは安心感につながります。
人形供養はどこでできるのか?
では、人形供養はどこで行えるのでしょうか。
一般的には、以下のような場所で受け付けています。
- ・寺院や神社
人形を受け取り、僧侶や神職が読経・祝詞をあげて供養します。
毎年決まった日に「人形供養祭」を行う寺社も多くあります。 - ・葬儀社や霊園
葬儀社の中には人形供養をサービスの一環として受け付けるところもあります。
霊園や墓苑で合同供養祭を実施するケースも増えています。 - ・人形供養を専門に扱う団体
郵送で受け付ける仕組みを整えている団体もあり、遠方からでも依頼が可能です。
近年では海外で日本人形の人気が伸びており海外へ輸出されたり、海外の児童施設に寄付されるケースもあるようです。
流れと費用について
供養の流れは、まず人形を持ち込み、読経や祝詞をあげてもらいます。
その後、お焚き上げをして浄火に還すか、寺院で丁重に処分されます。
近年は環境配慮の観点から「焼却処分」を避け、専用の方法で処理する施設もあります。
費用は数千円から一万円程度が目安で、人形の数や大きさによって異なります。
人形と一緒に写真や手紙を納められることもあり、最後のお別れとして心を込められるのも特徴です。
まとめ
人形供養は「処分」ではなく「感謝を込めたお見送り」。
長年寄り添ってくれた人形に手を合わせて送り出すことは、自分の心を整理することにもつながります。
思い出の品を前向きに手放すための方法として、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。
「普通のお葬式」では様々なご相談、ご紹介を承っております。
普通のお葬式では、お葬式、法事、終活に関するお困りごとなど、様々な専門知識を要する内容のお手伝いやご紹介させて頂いております。「普通のお葬式お客様サポートダイヤル(0120-333-841)」まで、お気軽にお問い合わせください。詳しくはこちらから。
関連コラム

故人の遺品整理について
葬儀が終わった後、故人の遺品整理は避けて通れない重要なプロセスです。遺品整理は、故人を偲ぶ時間であると同時に、残された家族にとって新しい生活の一歩を踏み出すための準備でもあります。ここでは、遺品整理を進める上でのポイントを紹介します。

葬儀後の手続きと良くある困りごと
葬儀が終わった後、遺族には多くの手続きが待っています。この時期は、精神的な疲れや悲しみを抱えながら進める必要があり、負担が大きいと感じる方が多いです。普通のお葬式コラムでは、葬儀後に必要な手続きと、よくある困りごとについて解説します。

喪中ハガキ その2 〜喪中ハガキの作成・マナー〜
今回の普通のお葬式コラムは、前回に続き年末までに用意しなければいけない喪中ハガキについてのマナーや疑問について解説します。
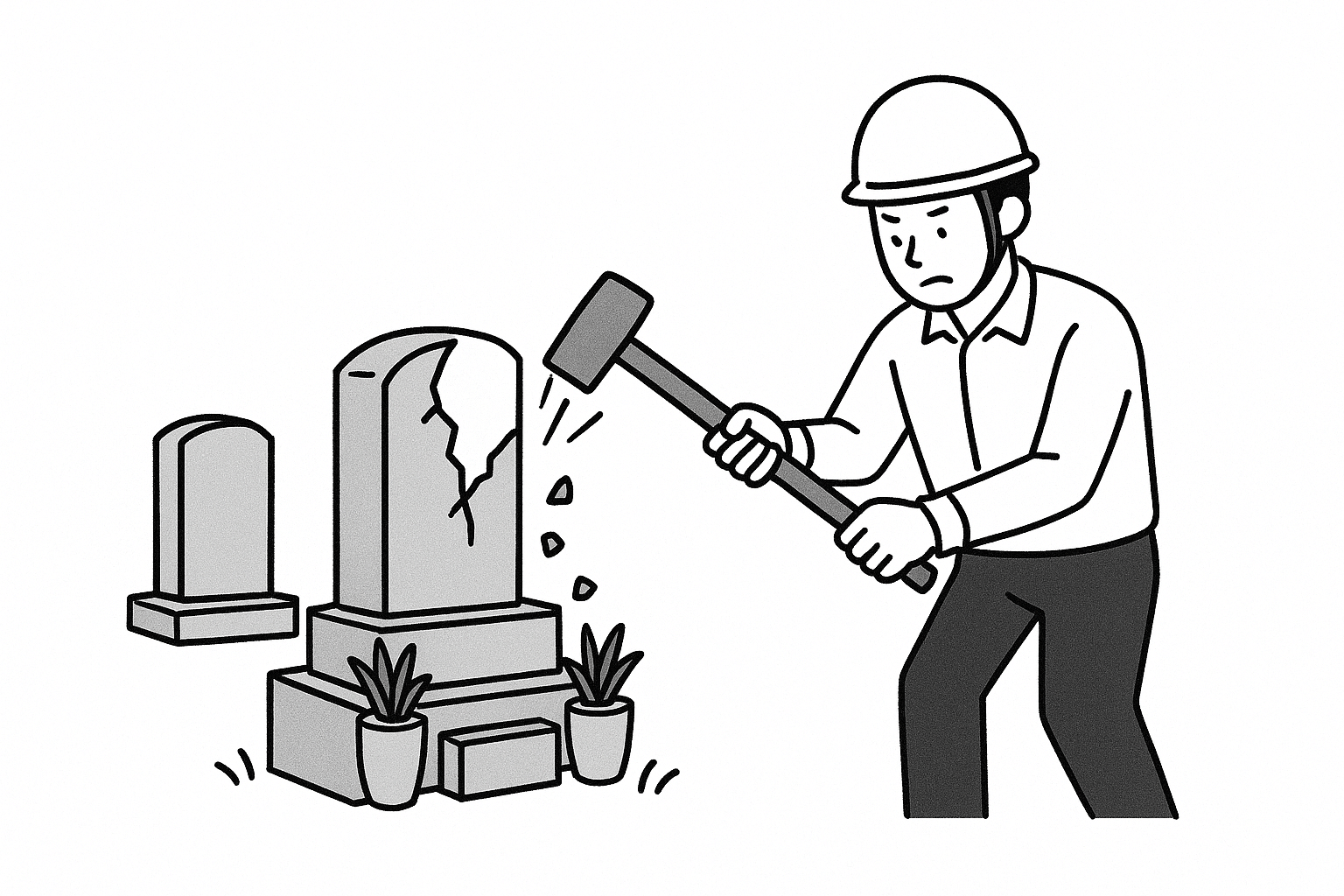
墓じまいについて
墓じまいとは何か、メリット・デメリット、費用相場や必要な手続きまで分かりやすく解説。後悔しない墓じまいのための基礎知識をご紹介します。