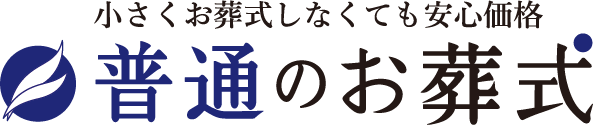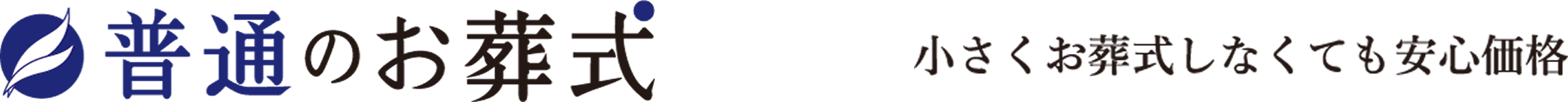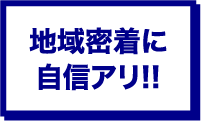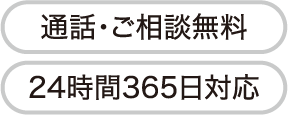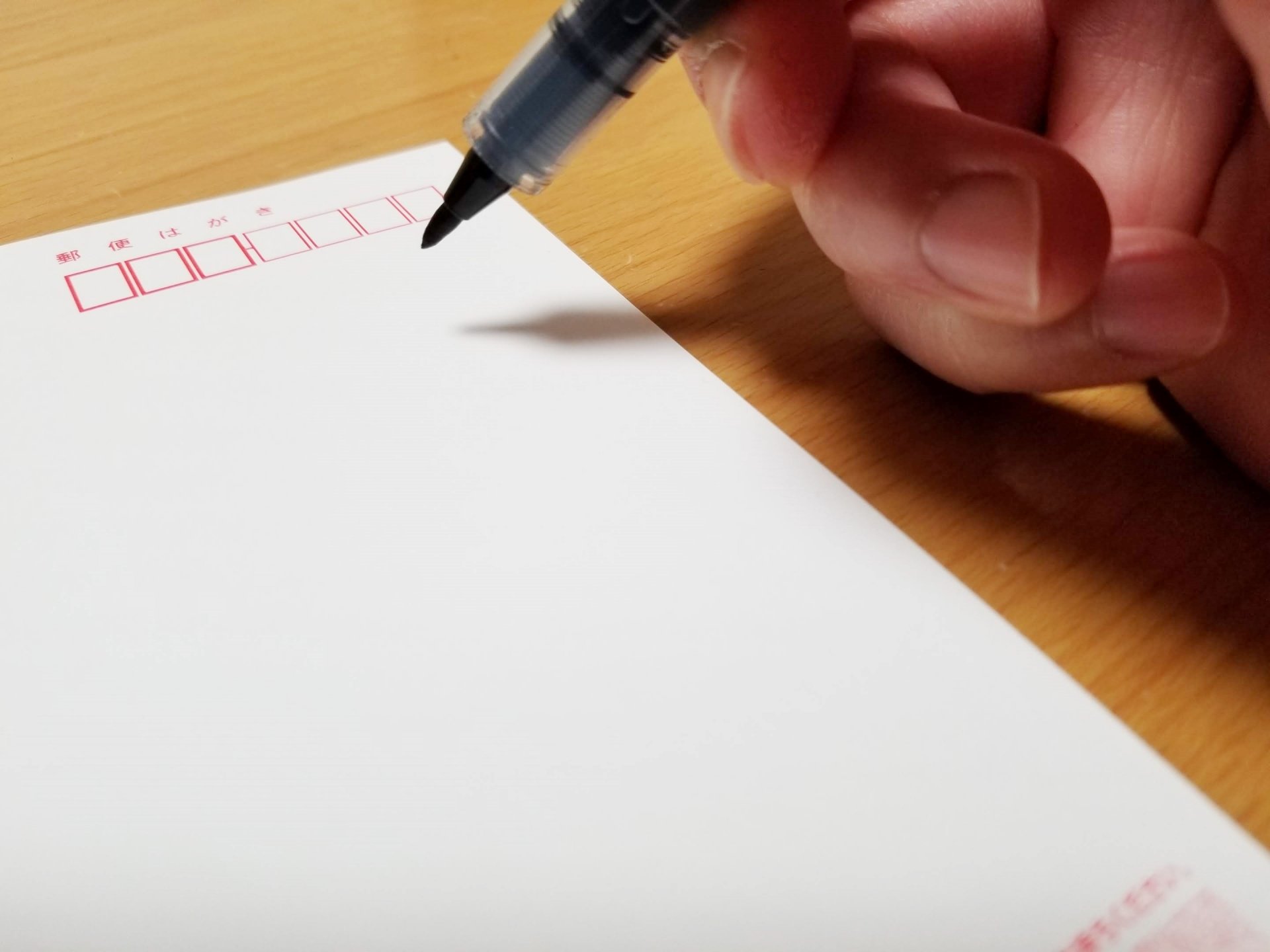
喪中ハガキ その1 〜喪中の範囲〜
ご家族に不幸があった場合に、秋から冬になる前に喪中ハガキの準備が必要となります。
今回の普通のお葬式コラムは喪中ハガキについて解説します。
喪中とは。。。どういうことでしょう?
昔から近親者が亡くなった時には、故人を弔うために日常生活の一部の行動を慎むという考えがあり、これを「喪に服す」といいます。 喪に服す期間には「忌中」と「喪中」があります。
忌中と喪中の期間は?
一般的に「忌中」は亡くなられてから50日間とされています。神道の考え方である「死の穢れ」が身内にも残っているとされる期間です。仏教で言いますと、忌明けとなる「四十九日まで」という捉え方になります。
「喪中」は遺族が故人を偲び、悲しみを癒し通常の生活に戻るための「忌中」を含む期間とされており、一般的には、配偶者や一親等の方は12~13ヵ月ほど、二親等の方は3~6ヵ月ほどとされています。

喪に服す範囲は?
一般的には「2親等以内の血縁者が亡くなった場合」は喪に服す、とされています。ただし諸説がありまして、「喪中」の範囲や期間については2親等内でも同居・非同居で喪中の期間が違う・2親等内でも血縁でなければ喪中にならないなど、状況に応じて分かれています。
喪に服している時にしてはいけないことは?
初詣や七五三などの神社へのお参り・結婚式へ出席・お祭りなどお祝いの場所への出席、新年のご挨拶、行楽行事(イベント的な行事)への参加などはNGとされていました。しかし、現代ではそこまで厳しく言う人はあまりいなくなっています。
「今の自分たちの生活」も大切に
忌中・喪中の考え方は儒教の思想に沿って決めたルールに基づいたものになっていますが、生活スタイルが変化する中で「現実的に無理じゃないか?」というものも出てきます。故人を偲ぶ気持ちは大切ですが、しきたりにこだわりすぎて日常生活に支障が出たり、人付き合いに影響が出るような場合は何が何でも従わないといけないものではありません。忌中に結婚式の予定がすでに入っていたり、町内行事のお祭りにはお手伝いに行かないといけない等の場合は、相手に忌中であることを念の為に伝えた上で参加しても良いのではないかと考えます。
「普通のお葬式」では様々なご相談、ご紹介を承っております。
普通のお葬式では、お葬式、法事、終活に関するお困りごとなど、様々な専門知識を要する内容のお手伝いやご紹介させて頂いております。「普通のお葬式お客様サポートダイヤル(0120-333-841)」まで、お気軽にお問い合わせください。詳しくはこちらから。
関連リンク
コラム「暑中見舞いは出してもいいの?」
関連コラム

大切にしてきた人形の処分に困る時
子どもの成長を見守ってきた雛人形や五月人形、思い出の詰まったぬいぐるみ。「捨てるのは忍びないけれど、どうしたらいいのだろう」と迷う方は少なくありません。そんな時に選ばれるのが「人形供養」です。

永代供養とは
永代供養とは、継承してくれる方がいないなどの理由でお墓を持てない方に代わり、寺院や霊園でご遺骨を預かり供養や管理を行ってくれる供養の方法です。

亡くなった方のスマホやインターネットはどうすればいいの?
家族が亡くなると死亡後の様々な手続きが必要となります。年金や健康保険、死亡届などは思い浮かびますが、近年必要とされる手続きにスマホやインターネット、サブスクが含まれるようになりました。今回の普通のお葬式コラムでは亡くなられた方のスマホ・インターネット・サブスクの解約手続きをどうやって進めるのか解説します。

葬儀後の手続きと良くある困りごと
葬儀が終わった後、遺族には多くの手続きが待っています。この時期は、精神的な疲れや悲しみを抱えながら進める必要があり、負担が大きいと感じる方が多いです。普通のお葬式コラムでは、葬儀後に必要な手続きと、よくある困りごとについて解説します。